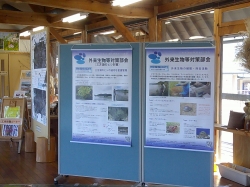暖かい日が多かった2月が過ぎ、冷たく寒い日が続く3月ですが、
先日は、北陸新幹線が敦賀まで延伸されました。
これからも笑顔で、お客様と新幹線をお迎えしたいと思います。
せっかくの機会ですので、自然観察棟を改めてご紹介いたします。
「道の駅 三方五湖」に隣接する木造の建物。
木製の階段を上っていくと、展望デッキがあり、右手に観察棟への入り口があります。

入っていただくとすぐに大きな水槽が目に入ります。
目の前の三方湖に棲んでいる魚たちを展示しています。
今は、昨年の6月に捕獲された大きなウナギが来館者の皆様を楽しませています。

三方湖に面する大きな窓の近くには、望遠鏡を多数設置し、
バードウォッチングを楽しむことができます。
肉眼では点のようにしか見えない大きさですが、望遠鏡を通すと
びっくりするくらい大きくはっきりと、そして、羽の模様まで見ていただくことができます。

反対側には、工作コーナー。
木の実やまつぼっくり、木の枝などを使って、工作を楽しんでいただいています。
ホットボンドで接着しますので、自由に組み合わせることができます。
小さいお子様でも楽しんで作っていただいています。

こちらは、今までに作られた作品の数々。

その他、研究員の発表や、地域のお子様の作品などを展示することもあります。
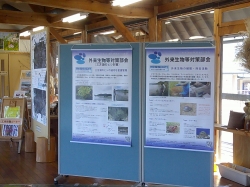
皆様、ぜひ、観察棟へお越しください。お待ちしています。